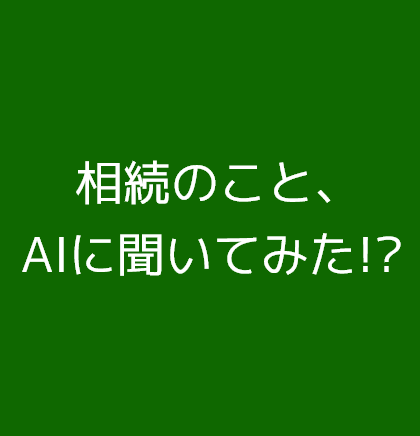父の遺言書は、法定相続分とは異なる割合で書かれています。この遺言書は法的に認められるのでしょうか。
申し訳ありませんが、私は法的なアドバイスを提供することはできません。相続法は国や地域によって異なり、遺言書の法的な有効性や相続人の権利に関する詳細な規定が存在します。
一般的には、遺言書が適切な形式で作成され、法定相続分や他の制約に違反していない場合、遺言書は法的に認められる可能性があります。ただし、具体的な法的効力を判断するためには、相続法の専門家や弁護士に相談することが重要です。
※原文のまま掲載
法定相続分というのは、民法上規定されている遺産の分配割合のことで、親族間で遺産を分配するにあたり、被相続人との関係の深さや公平性を考慮して各相続人の取り分を規定しています。
被相続人が遺言を残さなかった場合には、相続人同士が話し合って遺産を分配しなければなりませんが、法定相続分はその際の指標として機能します。
被相続人が遺言書を残していた場合は、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。
法定相続分(法律)よりも遺言書が優先されるのは、我が国の私的自治の原則と所有権絶対の原則が働くからとされています。
・私的自治の原則…私人間の関係については原則として国家はできるだけ干渉しない
・所有権絶対の原則…自分の所有する財産の扱いについては何者の干渉を受けず自由に決めることができる
生前の所有財産の扱いについて、遺言書でどのように指定するかは自由ということで、遺言書がある場合には、法定相続分より優先されることとなるのです。
ただし、法定相続分とは別の問題として、実際に遺言書が残されていたとしても残された遺族は別途遺産分割協議を行って、相続人全員の合意があれば遺言の内容と異なる分配内容にすることは可能です。
また、遺留分が侵害される遺言が残されていた場合には、所定の手続きをとることで遺留分を取り戻すことができるようになっています。全相続人分の総体的遺留分として次のとおりになります。
①直系尊属のみが遺留分権利者となる場合…相続財産の3分の1
②遺留分権利者が上記以外の場合…相続財産の2分の1
例えば子2人が相続人となる場合、各自の法定相続分は2分の1となり、総体的遺留分2分の1に法定相続分を乗じた4分の1が遺留分となります。
なお、遺留分権利者となれるのは、法定相続人のうち配偶者、子、直系尊属のみですので、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。