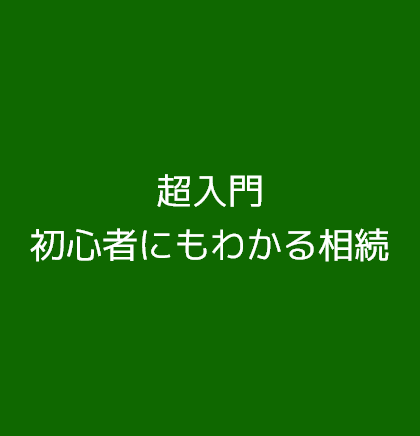被相続人は自分の財産について遺言をすることにより、法定相続分に優先して自由に分け与えることができます。
しかし、遺言によって、例えば「全財産を長男に与える」「長女には遺産を相続させない」といった遺言内容の場合、相続人間に不公平が生じ、財産をもらえなかった相続人は不満を持つことが懸念されます。
そこで「遺留分」という制度を設けて、相続人に一定の権利を認めています。
遺留分とは
遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、一定範囲の相続人ならば最低限相続できる財産の割合のことです。
遺留分は、たとえ被相続人であっても侵害できないことになっています。
遺留分の認められる範囲
民法では、配偶者、子(代襲相続人、養子を含む)及び直系尊属の相続人について遺留分を認めており、兄弟姉妹には認めていません。
したがって、相続人が配偶者と兄弟姉妹だけのときには、「全財産を妻に与える」という遺言を書いておけば、兄弟姉妹には遺留分が認められず、全財産が妻のものになります。
遺留分の割合
遺留分の割合は、法定相続割合の1/2または1/3と定められています。
配偶者がいる場合と配偶者がいない場合とで次のようになります。
【配偶者がいる場合】
- 配偶者と子の場合
配偶者は1/2×1/2=1/4、子1/2×1/2=1/4(複数人の場合は均等) - 配偶者と父母の場合配偶者は2/3×1/2=1/3、父母1/3×1/2=1/6(複数人の場合は均等)
- 配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者1/2、兄弟姉妹は遺留分なし
【配偶者がいない場合】
- 子だけの場合
子1/2(複数人の場合は均等) - 父母だけの場合
父母1/3(複数人の場合は均等) - 兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹は遺留分なし
遺留分の請求
相続した財産の額が遺留分に満たない、つまり遺留分が侵害された場合には、その侵害された範囲内で、「遺留分侵害額請求」という手続きをすることにより財産を取り戻すことができます。
遺留分が侵害されたとしても、相続人が遺言の内容について納得しているのであれば、その通りに遺産の分割が行われます。
また、遺留分が侵害されていることに不服があっても、相続の開始日、あるいは自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に遺留分侵害額請求をしなければ、その権利を放棄したものとみなされます。
自分の遺留分が侵害されていることを知らなかった場合でも、相続開始日から10年以内に遺留分侵害額請求権の行使をしなければ時効により消滅しますので注意が必要です。
遺留分計算のもととなる財産
遺留分計算のもととなる財産(被相続人の財産)は、相続時に有していた財産(※1)に生前贈与財産(※2)を加えたものから被相続人の債務を引いたものです。
※1 受取人が指定されている死亡保険金等は原則含まれません。
※2 相続人以外に対する生前贈与の場合は、相続開始前1年以内に行ったもの、相続人に対する生前贈与は、相続開始前10年以内に行った特別受益にあたる生前贈与が対象になります。